水 戸 八 景
|
水戸八景とは、水戸徳川家第九代藩主斉昭公(烈公)が、天保4年(1833年)に領内を巡視し八つの景勝地を
選定したものである。斉昭が藩主を継いだ頃の世情は、決して無事安穏ではなかった。英明で覇気に富んでいた
公であっても、心をわずらわすことが多かったであろうから、八景の風景は公の憂いを散らすに役立ったに相違
ない。しかし、八景設定の大きな目的は、藩内の子弟に八景巡りをすすめて、自然鑑賞と健脚鍛錬とを図ること
にあったのである。当時の流行語を用いれば、正に「文武両道の修練」に資せられたもので、公の深慮の程には
全く、感嘆してしまう。 |
|
生前の実名を 家康(11男5女)11男ー水戸家初代藩主 |
私が当時を振り返って歩いたコースを紹介します、当時は約90キロ(22里)の区間を徒歩で回った
現在は車で移動、約半日で全コースを回れます。
画像をクリックで拡大! 戻すときはブラウザの
 戻る で戻して下さい。
戻る で戻して下さい。画像下の文字をクリックで各コーナーへ
各碑文をクリックで各々場所へ移動します
|

|
| 弘道館へGO |
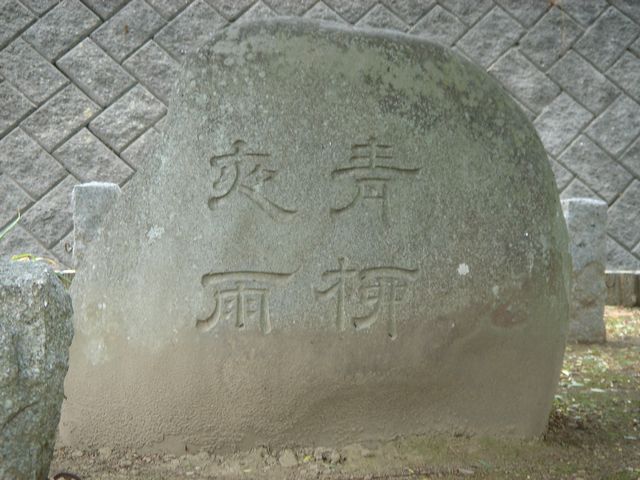 |
 |
 |
 |
| 青柳の夜の雨へGO | 山寺の晩鐘へGO | 太田の落雁へGO | 村松の晴嵐へGO |
 |
 |
 |
 |
| 水門の帰帆へGO | 岩舟の夕照へGO | 広浦の秋の月へGO | 仙湖の暮雪へGO |
水戸八景トップに戻る 弘道館へ 青柳の夜の雨へ 山寺の晩鐘へ 太田の落雁へ 村松の晴嵐へ
水門の帰帆へ 岩舟の夕照へ 広浦の秋の月へ 仙湖の暮雪へ